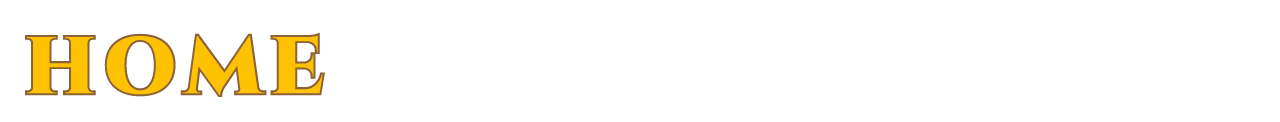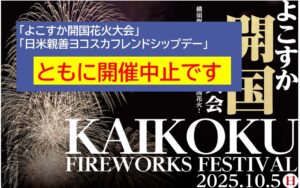小江戸(こえど)と言えば埼玉県の川越が有名ですが、「小江戸」という呼び名は、江戸(東京)を思わせる風情や城下町の面影が色濃く残る町につけられる愛称です。「小江戸」と呼ばれる条件は、主に以下です。
・江戸時代の城下町や商家町の面影が色濃く残る。
・蔵造りの町並みや水運の文化が残っている。
・江戸と交易や結びつきが深かった。※代表的な町は以下の通りです。
・江戸時代の城下町や商家町の面影が色濃く残る。
・蔵造りの町並みや水運の文化が残っている。
・江戸と交易や結びつきが深かった。※代表的な町は以下の通りです。
◆川越(埼玉県)
最も有名で、「小江戸」と言えばまず川越を指します。蔵造りの町並み、時の鐘、川越祭りなどが有名です。
◆佐原(千葉県香取市)
利根川水運で栄えた商家町。小野川沿いの町並みが「水郷の小江戸」と呼ばれ、重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。
◆栃木市(栃木県)
巴波川(うずまがわ)沿いに蔵が立ち並び、舟運で繁栄しました。「北関東の小江戸」とも呼ばれます。
◆喜多方(福島県)
蔵の町として知られ、蔵造りの建物が点在。ラーメンの町としても全国的に有名ですが、「蔵の小江戸」としても親しまれています。
◆大洲(愛媛県)
「伊予の小京都」と呼ばれることも多いですが、大洲城と城下町の風情から「伊予の小江戸」とも紹介されます。※一般的には「川越・佐原・栃木」が「関東三小江戸」と呼ばれ、特に有名です。中でも「小江戸川越」は有名でしょう。
最も有名で、「小江戸」と言えばまず川越を指します。蔵造りの町並み、時の鐘、川越祭りなどが有名です。
◆佐原(千葉県香取市)
利根川水運で栄えた商家町。小野川沿いの町並みが「水郷の小江戸」と呼ばれ、重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。
◆栃木市(栃木県)
巴波川(うずまがわ)沿いに蔵が立ち並び、舟運で繁栄しました。「北関東の小江戸」とも呼ばれます。
◆喜多方(福島県)
蔵の町として知られ、蔵造りの建物が点在。ラーメンの町としても全国的に有名ですが、「蔵の小江戸」としても親しまれています。
◆大洲(愛媛県)
「伊予の小京都」と呼ばれることも多いですが、大洲城と城下町の風情から「伊予の小江戸」とも紹介されます。※一般的には「川越・佐原・栃木」が「関東三小江戸」と呼ばれ、特に有名です。中でも「小江戸川越」は有名でしょう。